こんにちは、きょんです!
先日Xでたまたま見たのですが、
語彙を増やす有効な方法についての論文が取り上げられていました。
何度も書くけど、語彙力高めるには学習するより読書したほうが、短期的にも長期的にもよっぽど効率的だったという研究結果は衝撃的だよな。しかも複数研究のレビューなので、エビデンス・レベルが高い。
— Masanari Sakurai (@wagashi_no_yosa) February 28, 2025
こちらのポストにもう結論は書かれていますが、語彙を伸ばす有効な方法は「読書」とのことです。
エビデンス・レベルもメタアナリシスなので高いとされています。
ちなみにここで言われている「語彙」とは「学術語彙」と言われているもので、
抽象的、概念的な語彙です。日常生活で使われる語彙ではありません。
また、対象は英語となっています。
こういう知見をどう活用できると思いますか?
私のような子ども支援の現場で働いていると、検査や面接などから語彙不足を感じる子達がいる訳ですね。
語彙不足であることを保護者に伝えると「語彙を増やすにはどうしたらいいですか?」と聞かれることが多いです。
そういうときに、エビデンスを基に「本を読むことがよい」と伝えられると説得力も増しますよね。
実際にはこの論文だけを根拠に「とにかく読書を!」みたいな助言はしませんが
(だってそもそも読書苦手な子も多いし)、理屈として知っておくことは大切。
ということで以下に論文をまとめました。
見ていきましょう。元論文はこちら。タイトルは、
Where Do We Get Our Academic Vocabulary? Comparing the Efficiency of Direct Instruction and Free Voluntary Reading.
(学術語彙はどこから得られるのか?直接指導と自由自発的読書の効率性の比較)
著者はJeff McQuillan氏。2019年、THE READING MATRIX 19(1):129-138に掲載。
1.研究の目的
本研究は、学術語彙習得における2つの主要なアプローチ―明示的な語彙指導(直接指導)と、自由自発的な読書(FVR)―の効率性を比較検討することを目的としている。従来、語彙習得は教室での直接指導に頼る傾向があったが、一方で言語獲得理論(Krashenの理解可能な入力説など)から、読書を通じた自然な語彙獲得の重要性も指摘されている。そこで、どちらのアプローチがより効果的に学術語彙を獲得できるのか、その定量的な違いと教育現場における実用性について検証することが本研究の狙いである。
2.背景
語彙は言語理解や学習に不可欠な要素であり、特に学術語彙は専門的な知識の習得や学問的文章の理解に直結する。しかし、学校現場では、低成績の生徒や第二言語学習者に対して十分な語彙習得が行われていないという問題が指摘されている。これまでの研究では、直接指導による体系的なアプローチが推奨される一方で、Krashenやその後の研究者たちは、自由な読書が豊富な語彙接触と反復露出をもたらし、より効率的に語彙を習得できる可能性を示唆している。さらに、一般語彙の充実が学術語彙習得の基盤となる点も注目され、両者の関係性が教育実践において再考される必要があると考えられている。
3.研究方法
本論文では、2つのアプローチについて以下の方法で効果を評価している。
【直接指導(※)】
・過去に実施された大規模な語彙介入研究7件のデータを再分析し、実際に授業内で指導された語彙数やその学習効率を、1分あたりに習得される単語数(words per minute; wpm)として算出。
【自由自発的読書】
・米国の小中学生に人気のあるヤングアダルトフィクション22冊から、約100万語のテキストコーパスを構築。コーパス内で出現する学術語彙(Academic Word Listに準じる単語群)の頻度や、一定の出現回数を基準に習得済みと判断できる語数を推定することで、読書による語彙習得効率を評価した。この両手法の結果を比較し、各々の効率性や実践上のメリット・デメリットを明らかにしている。
※この論文での【直接指導】とは以下のような内容を指します。
ターゲット語の明示的提示と練習
教室内で特定の学術語彙(例:Academic Word Listに基づく単語群)を取り上げ、事前に選定した語彙を集中的に教えます。これには、語彙の意味や用法、文脈での使い方の説明が含まれます。多様なアクティビティの実施
例えば、Lesauxら(2014)の研究では、以下のような活動を各々最低10時間ずつ行うことが示されています。
・意味マッピング:単語の意味を視覚的に関連付ける活動
・文脈の手がかりの利用:例文や文章内の情報から意味を推測する練習
・辞書の定義の活用:正式な定義を参照しながら語彙の意味を深く理解する
・単語の生産的表現:図やその他の視覚資料を用いた創造的な表現
・形態素解析:単語を構成する要素(接頭辞、接尾辞、語根など)に分解して意味を探る
・模擬面接:目標単語を用いた対話形式の練習時間配分と効果測定
介入プログラムでは、授業時間のかなりの割合(しばしば全体の20~40%)が直接指導に充てられ、その成果は事前・事後の語彙テストによって評価されます。具体的には、1分あたりの習得語数(wpm)として算出され、平均約0.005語/wpmという数値で示されるなど、非常に限定的な成果しか得られていない点も明らかにされています。対象とする生徒層
多くの介入研究は、成績の低い中学生や英語学習者、言語的マイノリティの生徒を対象に実施されており、直接指導がこれらの生徒の語彙知識向上に果たす役割が検証されています。
4.主要な結果
再分析の結果、直接指導では1分あたり平均約0.005語の習得率に留まり、例えば毎日5分間の指導を180日続けた場合、1年間で習得できる学術語彙数は僅か4~5語程度と非常に低い結果となった。一方、自由自発的読書の場合、22冊のフィクションを通して推定される学術語彙習得数は113語から213語となり、1分あたりの習得効率は0.01~0.03語と算出された。つまり、読書を通じた語彙習得は直接指導の約2倍から6倍の効率を示し、自然な言語接触が学習効果に大きく寄与することが明らかになった。また、一般語彙と学術語彙は密接な関連性があり、自由読書による一般語彙の充実が、結果的に学術テキストの理解や学術語彙の習得を促進する効果も示唆されている。
5.結論と教育的示唆
本研究の結果は、従来の直接指導に基づく計画的な語彙教育では、限られた時間内で十分な語彙獲得が見込めない一方で、自由自発的な読書を通じた自然な言語接触が、効率的かつ大規模な学術語彙の獲得に寄与することを示している。さらに、読書は生徒にとって楽しく、自発的に行えるため、教師の負担も軽減される。こうしたことから、教育現場では、魅力的な読み物の提供と、十分な自由読書時間の確保が、語彙力全体の向上につながる効果的な介入策として推奨される。特に、一般語彙が充実すれば、学術テキストの理解が進み、より高度な学習へと発展するため、自由読書の推進は長期的な学習効果を期待できる重要な要素である。
6.著者の主張
著者Jeff McQuillanは、学術語彙習得において、直接的な語彙指導のみでは十分な効果を得ることが困難であり、むしろ生徒にとって自然で楽しい読書体験を通じた語彙習得が、より効率的かつ持続可能なアプローチであると強く主張している。彼は、自由読書が生徒に一般語彙を豊富に提供し、その結果、学術語彙の理解や習得を「架け橋」としてサポートする点に着目する。また、自由読書は教師にとっても実施の負担が少なく、長期的には生徒の学習意欲や総合的な言語能力の向上につながるため、今後の語彙指導方法としてより重視されるべきであると結論付けている。
以上です。
つまり、自由に読書をすることで一般語彙が獲得されて、それがひいては学術語彙の獲得をサポートするということですね。
結局、本人の関心にまかせた読書をさせる方がよいということになるのかもしれません。
その意味では、授業でテスト時間で早く終わった児童は読書タイムが与えられることがままありますが、
これは語彙獲得の有効なアプローチと考えられます。
最後に余談ですが、語彙の中でも「感情をあらわす語彙」が極端に少ない子たちと出会うことがあります。
要因はケースバイケースなのですが、語彙を増やすという点に特化して考えれば、
こういう書籍なども参考になります。
加えて言えば、これは若手心理職が自身の語彙を増やすためにも役に立つと思います。
Kindle本にしてスマホに入れておいて、時々見返して的確な語彙を確認することを繰り返して習得していく訳です。
最後までお読みいただきありがとうございました!
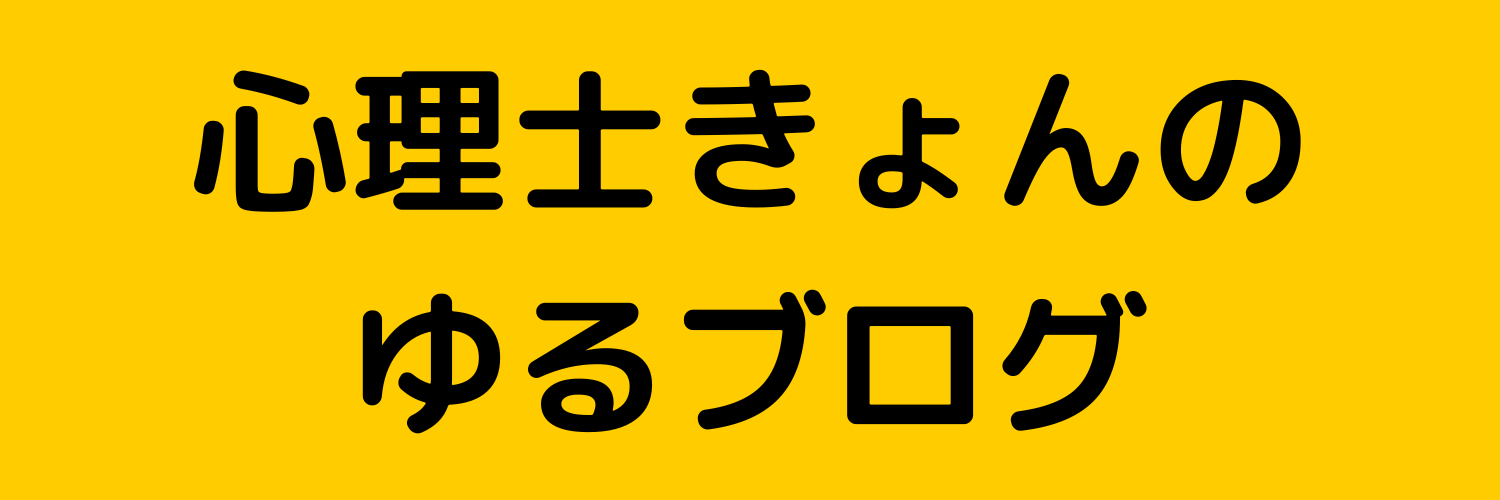


コメント